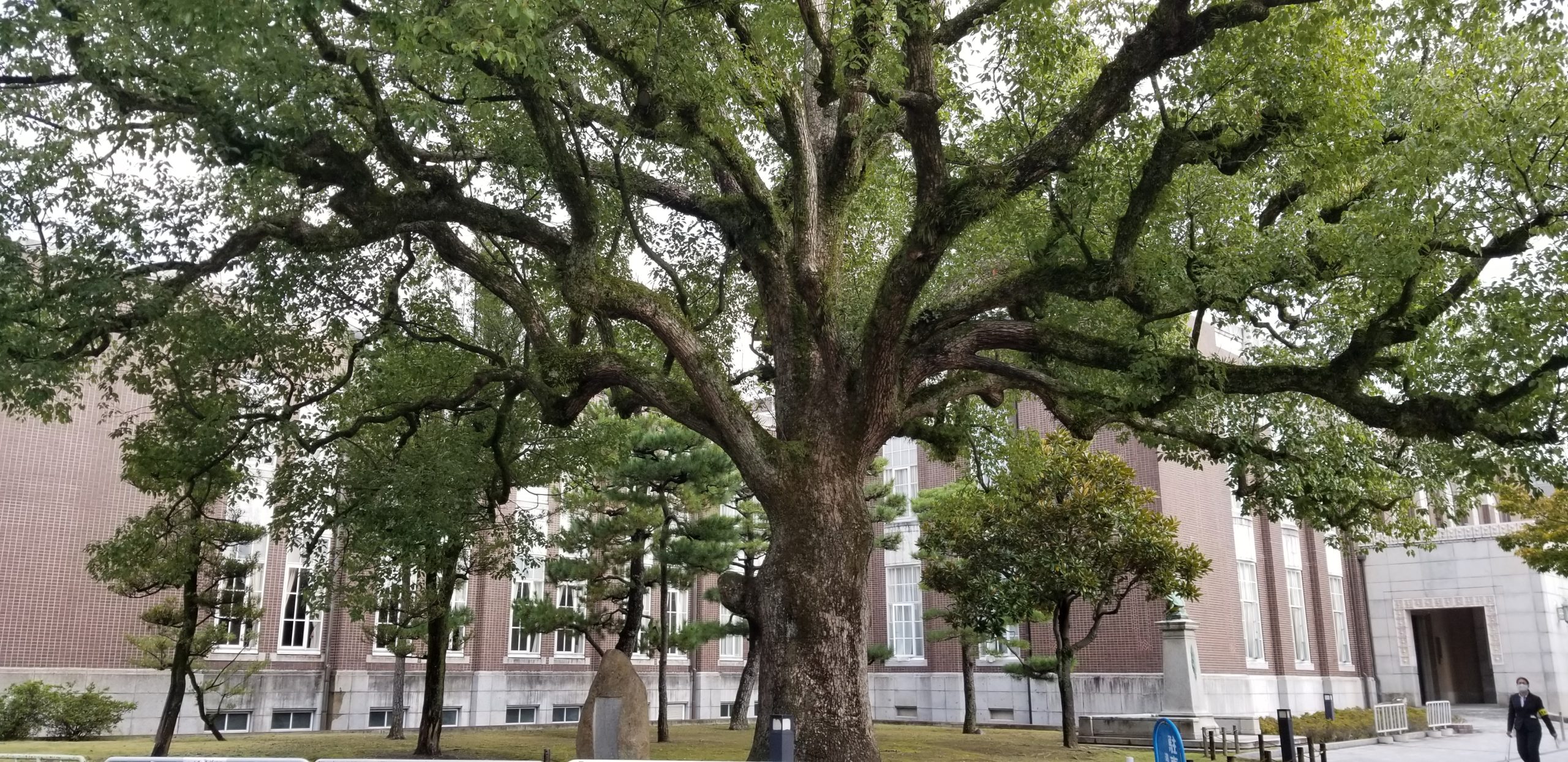水無月とは、白くて三角形のういろう状のものに甘く炊いた小豆をてんてんとのせ、氷をまねたものです。
昔、氷室という今でいう金閣寺の裏あたりに貯えられた氷雪を、6月30日(夏越の大祓・なごしのおおはらえ)に宮中(平安貴族)に献上する習わしがありました。
一般庶民には高価で貴重な手の届かない氷。
私たちは氷の形といえば製氷機から出てくる形を想像しますが、当時は、氷といえば三角形の形を連想されていたそうです。
三角形には他にも、四角を半分にすることで半年という意味もあって、残り半年の幸せという意味もあり素敵ですよね。
それをお菓子として目で涼をとって暑気払いをしていました。
上にのっている小豆は邪気を払うためのものです。
これは和菓子屋さんで作る作り方ではなく、電子レンジで簡単に子どもでも作れる作り方。


水無月をお抹茶と一緒にいただく。
クッキングを通して、料理だけでない京都の歴史を学べると、美味しくて理解が深まります。
朝の登校前の時間にもお抹茶で水無月。
小豆の甘味で、午前中の授業も集中力が高まってバッチリだね。


6月30日は水無月を買いました。
高島屋の食料品売り場では約30種類もの水無月があります。
平安時代の人と同じように、現代でも京都の人が6月30日に同じ和菓子の水無月を食べていると考えるだけで面白いですね。
プレーンなものと、抹茶味と、黒糖の3種類を2個ずつ買いました。
今年の残り半年も、これで無病息災を祈ります。